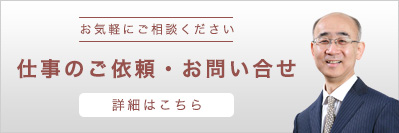2025年10月に『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕~なぜ、あのリーダーに部下はついていくのか』を出版いたしました。本書の目的は、リーダーシップの本質を明らかにした上で、若手管理職は何に対して、どのようにリーダーシップを発揮すればよいのかを、具体的にお伝えすることです。
そこで、様々な誤解がある「リーダーシップ」について、それを正しく理解するために、本書の「まえがき」を5回に分けてお届けします。
以下、『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』「はじめに」より
【重要ポイント3】リーダーシップが必要なマネジメントとそうでないものがある
上質のマネジメントに必須のリーダーシップですが、日々の業務でそれが意識されることは思いのほか多くありません。とくにリーダーシップを意識しなくても、管理職として日常のルーチン業務を回すことはできるからです。たとえば、次のような業務です。
リーダーシップを発揮しなくてもできるマネジメント
・部下の勤怠管
・スケジュール調整と進捗管理
・タスクの割り振りと、ルールや手順、法令に則った実行指示
・上司からの情報や指示の部下への伝達
・上司や他部門への連絡、報告、情報共有
・定められた評価シートによる部下の業績評価とフィードバック
・専門知識や専門スキルを生かした個別の仕事、部下の業務指導
・予算管理、経費の決済
これらは定まったルールや手順に則って実行する管理業務です。もちろんどれも大切な仕事ですが、一定レベルの知識と経験があれば可能です。ただし、これらは管理職がなすべき仕事のほんの一部でしかありません。これが管理職の仕事だと思ってしまうと、チームは、いつもと同じ仕事を、いつもと同じようにやって、いつもと同じ結果を出す――いつも通りの現状維持が関の山です。周りが急速に変化していく時代において、現状維持は相対的な退化を意味します。
変化に対応しながらチームの成果の最大化を目指していくためには、管理職は次のようなことに取り組んでいく必要があります。そこには、共感と行動を引き出すリーダーシップが必要です。
リーダーシップを発揮しなければできないマネジメント
・チームのビジョンやゴールの明確化、共有化、浸透
・目標に向けた戦術の策定と実行
・上質なチームワークとチーム文化の醸成、職場の心理的安全性の醸成
・他部門を巻き込んだ業務推進
・部下のモチベーションと成長意欲を刺激する環境整備
・深刻なトラブルや非常時における迅速かつ的確な意思決定と対策実行
・新しいアイデアの創出・具体化・実行、新しい価値観やプロセスの浸透
・部下の強みを生かした成長支援、部下のリーダーシップの開発
これらは手順が決まっている日常的な業務ではなく、チームの体質を改善してアウトプット力を高めていくための働きかけです。それによって、一過性の成果ではなく、持続的に成果を出せる上質のチームができあがっていきます。
これらは管理職の一方的な指示だけでなしえるほど簡単なものではなく、メンバーと力を合わせて積み上げていくものです。だからこそ、「自分が示すゴールに向けて人が共感して動く影響力」としてのリーダーシップを発揮することが必要なのです。
(続く)
リーダーシップの要諦(4/5)「あらゆるリーダーシップの本質は1つである」