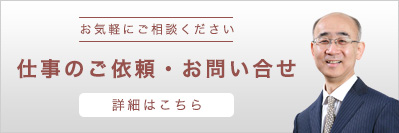2025年10月に『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕~なぜ、あのリーダーに部下はついていくのか』を出版いたしました。本書の目的は、リーダーシップの本質を明らかにした上で、若手管理職は何に対して、どのようにリーダーシップを発揮すればよいのかを、具体的にお伝えすることです。
そこで、様々な誤解がある「リーダーシップ」について、それを正しく理解するために、本書の「まえがき」を5回に分けてお届けします。
以下、『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』「はじめに」より
【重要ポイント5】 リーダーシップは経験と学習で身につけることができる
リーダーシップの本質は影響力ですが、影響力の「力」という文字は、専門能力、英会話力、コミュニケーション力などと同じ「能力」であることを示しています。能力は特定の役職や立場の人だけのものではありません。コミュニケーション力があらゆる人に必要な能力であるのと同じように、リーダーシップもあらゆる人に必要な能力であり、どのような人でも身につけて発揮しうるものです。
たとえば、議論が拡散して結論が見えなくなった会議で、Aさんが「いったん会議の目的に立ち返って論点を絞りませんか」と発言し、他の参加者が「確かにそうだよね」と賛同したとしたら、それは小さな行為ではありますがAさんのリーダーシップです。
経営レベルのリーダーシップもあります。大企業病でスピード感を失っていた企業の経営者が危機感を訴え、先頭に立って風土改革に乗り出し、社員が共感して変わり始めた、などがその例です。影響力としてのリーダーシップは、それぞれが置かれた立場に応じて、それぞれのレベルで発揮できるものです。
能力は経験と学習によって身につけて強化できるものです。リーダーシップも例外ではありません。チーム運営を始めたばかりのあなたも、様々なマネジメント経験を経ながらリーダーシップを強化していくことができます。その上で、どのようなタイプのマネジメントを行うかは、自分にふさわしいものを選択していけばよいのです。
ただし、リーダーシップの本質である「影響力」への正しい理解がないまま的外れな努力しても、リーダーシップは身につきません。「なぜ人は共感してついてくるのか?」といった人の行動原理への理解が必要です。その上で、自分にとって必要なことを強化していくことで、人がついてくるリーダーとしての影響力を高めることができます。この点についても本書の中で具体的に述べていきます。
日米企業の優れた管理職のリーダーシップ
ここで、少しだけ私のことを話します。私が初めて管理職になったのは36歳のとき、日興證券(当時)で課長として10人の部下を持ったときです。深海調査船の開発に携わっていた造船会社から転職して6年目のこと、そのときの緊張感を昨日のことのように覚えています。幸いにも、部下や上司、同僚に支えられながら、様々なマネジメント経験を積むことができました。その後、米国系資産運用会社ラッセル・インベストメントに転職し、資産運用コンサルティング部長、執行役COO(最高執行責任者)として米国人社長・CEO(最高経営責任者)とともに経営に携わります。
私は、このキャリアの中で出会ったハイパフォーマーの人たち(高い成果を出している人たち)から、たくさんの学びを得ることができました。とくにジョブ型雇用かつ成果主義のシステムで成果を求められる、日本企業の将来を先取りしたかのような米国企業での経験は、私を大きく成長させてくれました。
以上の経験を踏まえて出版した、『管理職1年目の教科書』(2017年)、改訂版の『新 管理職1年目の教科書』(2023年)は、おかげさまで、累計14刷り(2025年8月31日時点)と重版を重ねながらロングセラーとして多くの方々に読んでいただいています。
本書は、そこに流れる組織運営の基本的な考え方を軸としつつ、人と組織が主体的に動くための影響力としてのリーダーシップに、あらためて焦点を当てたものです。
外資系企業の世界では、管理職のリーダーシップはきわめて重視されています。チームの成果の最大化のためには、チームの方向性を示し、チームワークを築き、メンバーを育成し、チーム力を高めていくことが必須からです。
マネジャー(課長クラス)やディレクター(部長クラス)、マネジング・ディレクター(執行役員クラス)などの管理職ポジションを外部から採用するときも、前職でどのようにリーダーシップを発揮してきたのか、どのようにチームをつくってきたのは、必ず確認される重要なポイントです。いくら高い実績をアピールしても、実績の土台となるチーム力を強化するリーダーシップがなければ、組織マネジメントを任せることはできないからです。
いま、あなたがプレイングマネジャーとして実務とマネジメントの両立に苦心されていたとしたら、必要なものは気合いや根性、ましてや長時間労働ではありません。必要なものは、リーダーシップを正しく身につけ、メンバーへの影響力を発揮してチーム力を高めることです。それによって、実務の生産性もマネジメントの生産性も高まり、プレイングマネジャーとしてバランスのとれた管理職に成長していくからです。
リーダーシップを発揮すべき5つの項目
ここまでのリーダーシップに対する理解を踏まえた上で、本章では「若手管理職は何に対して、どのようにリーダーシップを発揮すればよいのか」を5つの章で述べていきます。さらに第6章で、人の行動原理を明らかにした上で、人がついてくる影響力をどう高めていていけばよいかについて述べます。
第1章 ベクトルをそろえるリーダーシップ――視線のベクトルと行動のベクトル
第2章 チームワークを築くリーダーシップ――協調性ではなく貢献性を求める
第3章 問題を解決するリーダーシップ――現象ではなく不都合に目を向ける
第4章 周りを巻き込むリーダーシップ――相互理解と”Win-Win”を築く
第5章 リーダーシップ文化を醸成する――リーダーシップの総量を増やす
第6章 リーダーシップを磨く――信頼に基づく影響力の3要素
本書でお伝えすることは、特定の企業や組織の中だけに限らず、人と人との関係性が存在する組織であればどこでも通用するものです。ただし、人には人それぞれの価値観や得意、不得意があります。各章で紹介する内容と背後にある理由を理解して、あなたに合った形でリーダーシップを身につけて発揮していくことが、チームの成果と、あなたとメンバーの成長につながります。
本書が、変わりゆく時代の中で管理職としての第一歩を踏み出したあなたが、縁あって部下となったメンバーとともに、良き職業人生を送っていくための一助となれば幸いです。