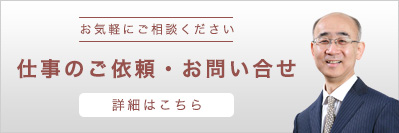2025年10月に『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕~なぜ、あのリーダーに部下はついていくのか』を出版いたしました。本書の目的は、リーダーシップの本質を明らかにした上で、若手管理職は何に対して、どのようにリーダーシップを発揮すればよいのかを、具体的にお伝えすることです。
そこで、様々な誤解がある「リーダーシップ」について、それを正しく理解するために、本書の「まえがき」を5回に分けてお届けします。
以下、『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』「はじめに」より
【重要ポイント2】リーダーシップとマネジメントはまったく別のものである
管理職の本質的な役割は、「チームの成果の最大化」です。何がチームの成果であるかは仕事の内容やチームの役割によって様々ですが、企業内に人が配置された組織が存在するということは、そこに期待される役割と求められる成果があるからです。
それは、数値化できるものであったり、定性的なものであったりしますが、期待される役割のもとで求められる成果の質または量、あるいはその両方を最大化することが管理職としての仕事です。
仕事の役割分担や進捗管理はもちろんのこと、会議、効率化、意思決定、他部門との調整、部下の育成や新しい取り組みにいたるまで、すべてチームの成果の最大化へ向けての活動です。
リーダーシップと混同されやすい言葉にマネジメントがありますが、両者には明確な違いがあります。
「リーダーシップ」が、人に働きかける影響力という「能力」であるのに対して、「マネジメント」とは、チームの成果の最大化に向けて、与えられたヒト・モノ・カネを使って効率的かつ効果的に組織運営を行う「役割」のことです。
企業の場合は、組織ごとの責任者である部長や課長などにマネジメントという役割が与えられ、その役割を与えられた人が、いわゆるマネジャー(管理職)です。
マネジメントは単なる業務管理を意味しているのではなく、目標に向けた業務計画策定、最適な人材配置、円滑な業務推進のための仕組みやルールづくり、メンバーの成長支援などを含めて、チームのアウトプットを高い生産性で生み出す推進機能でなくてはなりません。
障害となっている問題を解決することや、関係部署との協力体制を築くこともマネジメントの1つです。
上質なマネジメントのためには、目指すゴールへ向けて人が喜んで動いてくれることが必要です。つまり、管理職が担うチーム・マネジメントという役割を、高い質で行うために必須の能力(影響力)がリーダーシップなのです。
「役割」としてのマネジメントと「能力」としてのリーダーシップは、密接な関係はあっても種類の異なるものです。同列に比較したり、どちらが重要であるかなどを議論したりすることにはまったく意味がありません。
(続く)
リーダーシップの要諦(3/5)「リーダーシップの必要なマネジメントとそうでないものがある」