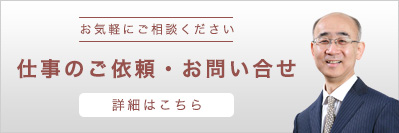2025年10月に『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕~なぜ、あのリーダーに部下はついていくのか』を出版いたしました。本書の目的は、リーダーシップの本質を明らかにした上で、若手管理職は何に対して、どのようにリーダーシップを発揮すればよいのかを、具体的にお伝えすることです。
そこで、様々な誤解がある「リーダーシップ」について、それを正しく理解するために、本書の「まえがき」を5回に分けてお届けします。
以下、『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』「はじめに」より
本書の目的は、リーダーシップの本質を明らかにした上で、若手管理職は何に対して、どのようにリーダーシップを発揮すればよいのかを、具体的にお伝えすることです。
急速な技術革新をともないビジネス環境や労働環境が大きく変わりつつあるいま、中間管理職に対する経営者の強い期待を感じます。とくに最近、経営者の方々が頻繁に口にする言葉が「リーダーシップ」です。正解のない問題への対応や、価値観の異なる多様な社員のマネジメントを、現場の第一線に立つ中間管理職の皆さんが、迅速かつ的確にリードしていく組織のダイナミズムを期待されているのです。
ただ、このリーダーシップという言葉はきわめて抽象的なものです。管理職のリーダーシップに期待すると話している、経営者自身の解釈もそれぞれです。しかも世の中には、牽(けん)引型リーダーシップ、支援型リーダーシップ、変革型リーダーシップなどの様々なリーダーシップ論が氾濫しています。
若手管理職の皆さんの多くはマネジメント経験が浅い上に、プレイングマネジャーとして実務とマネジメントの両立に苦労されていることと思います。その状況でリーダーシップと言われても、「そもそもリーダーシップって何?」「マネジメントとどう違うの?」「何に対してリーダーシップを発揮すればよいの?」「どうすれば部下はついてくるの?」といった疑問が頭をよぎるのではないかと思います。
本書はそのような皆さんの疑問にお答えするものです。
リーダーシップを正しく理解して、それを発揮している管理職と、誤った理解でリーダーシップを発揮できていない管理職とでは、チームの成果に大きな差が生まれます。その差は、顧客や会社からの評価はもちろん、ビジネスパーソンとしての自分自身の人材価値にまで影響します。そこで、本章に入る前に、リーダーシップを正しく理解するための重要な5つのポイントを紹介します。
【重要ポイント1】 リーダーシップの本質は影響力である
そもそもリーダーシップとは何でしょうか。次のような場面を想像してみてください。
あなたが「チーム内の協力体制をもっと高めたい」と伝えて、部下たちが「ぜひ、やりましょう。私たちもアイデアを考えます」と返ってきた。厳しい局面で、「よし、○○でいこう」と決断し、それを伝えた部下たちが「○○さんの判断を信じます」と動き始めてくれた。他部門の管理職に「部門を超えた意見交換会を行いましょう」と提案し、相手が「いいですね、やりましょう」と共感して調整を始めてくれた。
いずれも、あなたが「○○をやろう!」と声をあげ、周りの人が「よし、やりましょう!」と共感して動き始めています。このような、人に働きかける影響力がリーダーシップです。本書では、リーダーシップを次のように定義します。
『リーダーシップとは、自分が示すゴールに向けて人が共感して動く影響力』
ここで強調したいのは、リーダーシップは「自分の思い通りに人を動かそうとする指示や命令」ではないという点です。課長や部長といった肩書きを押し出して、「つべこべ言わずにいいからやれ」というのは単なる権限行使です。
もちろん、チームの責任者として、権限行使が必要な局面は随所にあります。しかし、「権限行使だけ」に頼っていると、目指す方向や方針が納得できないまま不承不承従うやらされ感がチームを支配することになります。言われたことを言われたようにしかやらない自律性も創造性もないチームが、優れた成果を生み出せるとは思えません。
これに対してリーダーシップとは、「自分が望むように人が自ら動く」ための働きかけです。チームの成果は管理職だけが頑張るものではなく、メンバーと力を合わせてつくり上げていくものです。管理職はチームの責任者として方向を示し、そこへ向かってメンバーが足並みをそろえて動いていく状態をつくらなければなりません。しかし、人にはそれぞれの意思があり、最終的な行動を選択する自由があります。それでも、あなたの働きかけに対して「喜んで!」と応えてくれる―――この影響力がリーダーシップです。
このようなチームには活力と主体性が生まれ、チームは共通のゴールに向かって連携しながら進もうとする機能集団になります。権限行使だけに頼るチームとの成果の違いは明らかです。
(続く)
リーダーシップの要諦(2/5)「リーダーシップとマネジメントはまったく別のものである」