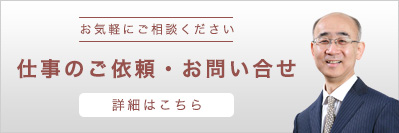「会社の中だけでなく外にも目を向けよう!」―――何度も繰り返しお伝え
してきたことですが、学校教育にもようやく、ちゃんと外に目を向ける動き
が出てきました。
今年度(2022年度)から高校の歴史の授業体系が変わります。学習指導要
領の改訂により、世界史と日本史を同じ時間軸で統合的に学習する「歴史総
合」が必修科目として導入されるのです。
現行は世界史と日本史は独立した科目となっており、世界の動きがどのよう
に日本に影響したのかがわかりにくくなっています。日本史教科書が鎖国状
態にあったと言うべきでしょうか。
しかも、世界史は必修科目ですが日本史は選択科目であり、日本史の学習が
中学校止まりという子どもを大量に排出してきました。
かねてから、多くの人たちが世界の歴史は1つであり日本史と世界史を分け
るのはおかしいと主張してきましたが(私も同感)、ようやく実現したかと
いう思いです。
-------------
ペリーの本当の目的は何だったのか?
-------------
たとえば、幕末にペリーはなぜ浦賀に来航海したのか?
日本史の教科書には、捕鯨船の燃料や食料を補給するための基地として日本
に開国を迫ったとありますが、それは表面的な理由に過ぎません。
アメリカはヨーロッパ各国のグローバル戦略に追随して、アジア地域への進
出を狙っていました。しかし、現状のインド洋航路では、石炭と食糧を補給
する拠点がヨーロッパ諸国によってガチガチに抑えられているため、彼らに
頭を下げながら航海するといった屈辱を味わっていました。
そこで、まだ手つかずの太平洋航路の開拓に目をつけたのです。奴隷制度の
廃止に備えて、それを埋めるための低賃金労働者をアジアに求めるといった
思惑もあったようです。
とはいえ、中国はすでにアヘン戦争の敗戦国としてイギリスの影響下に置か
れつつあるため、アジア戦略の拠点として狙いを絞ったのが、まだほとんど
手つかずの日本だったのです。
ただし、唯一の外交窓口であった長崎の出島は、ポルトガルを追い出したオ
ランダがすべての特権を手にして君臨していました。そこを窓口にすると、
今度はオランダの下に立たざるを得なくなる。そこで、出島から遠く離れた
浦賀だったのです。
徳川幕府が何度も出島を通して話をするよう求めたにもかかわらず、全く相
手にしなかったのも当然のことです。
すなわち、ペリーの浦賀来航は、欧州諸国としのぎを削ろうとしていたアメ
リカの、計算されたグローバル戦略の中で必然的に起きたことだったのです。
しかし、このことは今の日本史教科書からは読み取ることはできません。
外に目を向けるからこそ、日本で起きていることがよく理解できるのです。
-------------
「自分の出島」を持とう
-------------
これはほんの一例ですが、新設される「歴史総合」では、このように世界と
日本を横比較をしながら歴史を学ぶことになるでしょう。
「歴史総合」で対象とされる時代は18世紀以降ですが、「なぜそうなった
か?」を生徒自身が考えることをより一層重視しています。もしかしたら「ペ
リーはなぜ浦賀に来航したのか?」ということを、生徒たちは議論すること
になるかもしれませんね。
自分の仕事しか知らない人は自分の仕事を知らない。
しかし、外に目を向ければ、自分の仕事がよくわかってくる。
自分の会社しか知らない人は自分の会社を知らない。
しかし、外に目を向ければ、自分の仕事がよくわかってくる。
日本のことしか知らない人は日本を知らない。
しかし、外に目を向ければ、日本のことがよくわかってくる。
今年も、デジタル化をはじめとした大変化の中に私たちはいます。気づかな
いうちに鎖国しているなんてことにならないよう、「自分の出島」をしっか
りと持って外に目を向けていきましょう。