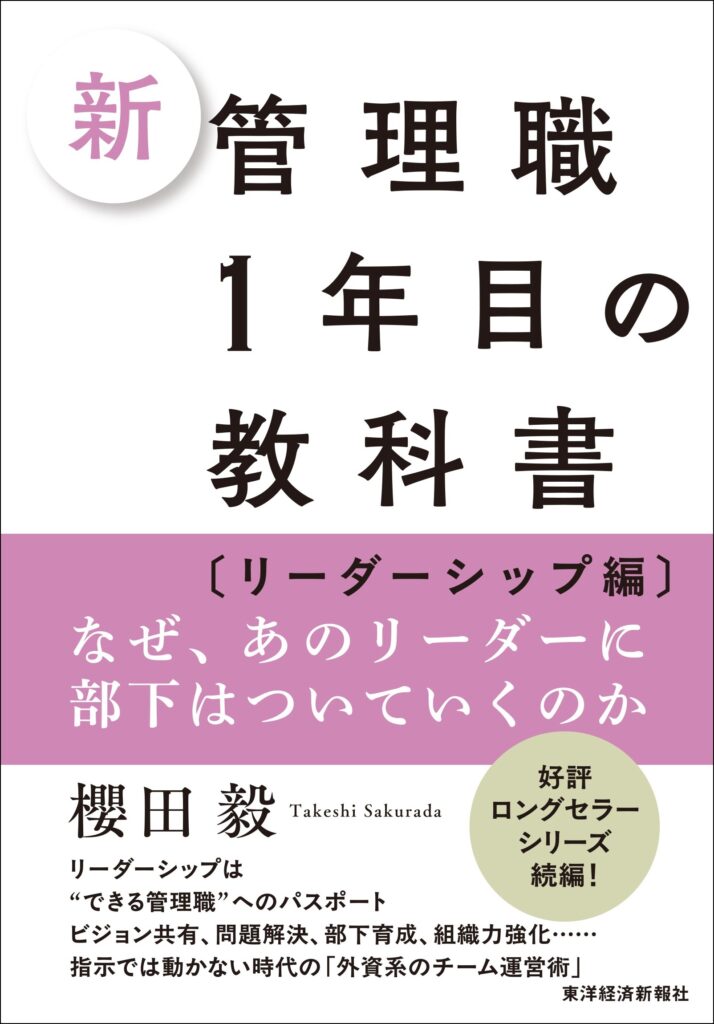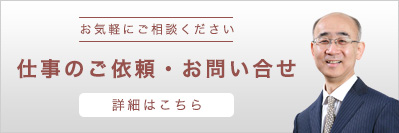仕事は「決めて、実行する」ことの繰り返しです。これを高い質で迅速に行うことが、優れた成果につながります。そのために組織のリーダーは、責任者としての意思決定を迅速かつ的確に行わなければなりません。
日本企業には合意形成を重んじる文化があります。決まったことを正確に繰り返せば成果が出た時代に、同質性のメンバーで納得感を共有することが、円滑な業務推進につながったからです。
一方で、いまのような正解のない時代では、最適解を導き出すために、多様な発想を活用するマネジメントが必要です。しかしながら、多様性を尊重すればするほど、全員が納得する結論を出すことは困難になります。無理な合意形成は得てして妥協の産物になりがちで、必ずしも最善のものとは限りません。
■ 会議の目的は優れた結論を出すこと
多様性を生かしながらも、仕事の質とスピードを維持する意思決定スタイルが「衆議独裁」です。
「衆議」とは、メンバーや関係者が意見を出し合い議論することです。様々な視点から問題を掘り下げたり、メンバー間や部門間の利害関係を明らかにしたりします。衆議では、同じゴールを目指している限り、忖度のない自由で多様な意見を歓迎します。
(続きはこちらから)

仕事は「決めて、実行する」ことの繰り返しです。これを高い質で迅速に行うことが、優れた成果につながります。そのために組織のリーダーは、責任者としての意思決定を迅速かつ的確に行わなければなりません。日本…
『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』から一部をピックアップして、オンライン用に加筆した内容です。